|
|
|
|
|
|
|
2013.11.17 / �Y���s |
|
�� �擪�����e�H�Ō������e�H�t�@�~���[�ł����ˁB
�i�O�o�Fyatyo12.htm
116�j |
|
 |
|
�I�i�K�K���F�J���� �J���� �S���i���J���j�Y
61-76cm�@��
51-57cm�i80-95cm�j�B�Y�͑̂��D�F�ōׂ����͗l������B���̓`���R���[�g�F�A���̌�납���A���͔��F�B���͔����B�K�A�e�i�킫�j�͒W���F�A�������͍��F�B���H�̒���2�������F�Œ����B�{�͏�ʂ͍������ʂ͐D�F�B���͊D���F�B�G�N���v�X*�͚{�̗������D�F�Ȃ̂ŋ�ʂł���B���͑S�̂����F�ō����F�̔��䂪�S�g�ɂ���B��͊��F�����Ă���B�������͔����B���������B�V�C�[�V�C�[���A�v���b�v���b�Ƃ������Ŗ��B |
|
�@��Ԃɐ��c�⎼�n�ɏo�č̉a����B�r�ȂǂŚ{�𐅂ɂ��ē������A�����Ƃ��ĐH�ׂ�B�t�������Ď�����Đ���̑͐ϕ������ށB���̃J���ނ�蒷����������Ă��邽�߁A�[������𗘗p�ł��邪�A�����ɐ����č̉a���邱�Ƃ͂Ȃ��B�G�H���ŁA�����̎�q��j�ЁA���������Ȃǂ�H�ׂ�B�a�t��������Ă���p���悭�ڂɂ���B
�ɐB������5�`7���ň�v��Ȃł���Ԃ͕������ɉ��������B |
|
*�G�N���v�X�F�J���ނ̗Y���ɐB���o�ߌ�A�ꎞ�I�Ɏ��̂悤�Ȓn���ȉH�F�ɂȂ��ԁB |
|
|
|
|
|
|
|
|
�I�i�K�K��
/ �Y���s�@2013.11.17 13:33 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1500�j545KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.11.23 /
�_�ސ쌧���쒬�_�싴 |
|
��
���ʂ���ŁA�������𐅒��ɓ���A��p�Ɉ��Ȃǂ�߂܂��܂��B���̎����͗������������A�Y��Ȏp�ŎB�e�ł��܂��B
�i�O�o�Fyatyo9.htm
88�j |
|
 |
|
�g�r�i�A�w���FMilvus migrans�j
�F�^�J�ڃ^�J�Ȃɑ����钹�ނ̈��B�g���r�Ƃ������B�قƂ�ljH�������ɔ��H�ōI�݂ɑǂ��Ƃ�A�㏸�C���ɏ���ėւ�`���Ȃ�����֕����オ��l��A�u�s�[�q�����������c�v�Ƃ��������͂悭�m���Ă���A���{�ł͂����Ƃ��g�߂Ȗҋחނł���B���[���V�A�嗤����A�t���J�嗤�A�I�[�X�g�����A�ɂ����čL�����z���Ă��邪�A����n�̂��͓̂~�ɂ͒g�n�Ɉړ�����B�����n�͍��R����s�s���܂łقƂ�Ǐꏊ��I���A���`�̎��ӂȂǂ͓��ɐ������������B�A�t���J�嗤�ɐ���������̂́A�j�V�g�r�Ƃ��ĕʎ�Ƃ��錩��������B |
|
�@�^�J�Ȃ̒��ł͔�r�I��^�ł���A�S����60-65cm�قǂŁA�J���X������傫���B���J����150-160cm�قǂɂȂ�B�������A�̏d�͌y���A�{��r�̗͎͂ア�B�̐F�͊��F�Ɣ��̂܂���͗l�ŁA��̎��͂������F�ɂȂ��Ă���B�n������ɂ���Ƃ��͔��H�̒��������ւ���ł��邪�A���ł���Ƃ��͔��H�̐�[�������B�܂��A���ł��鎞�͗��̐�[�߂��ɔ����͗l��������B |
|
�@�C�݁A���c�n�сA�͐�A�Ώ��̎��ӂȂǂɐ�������B��ɏ㏸�C���𗘗p���ėւ�`���悤�Ɋ��A�H�������Ƃ͏��Ȃ��B���͂����ɗD��Ă���Ƃ����A������Ă��Ȃ���a��T���A�a��������Ƃ��̏ꏊ�ɋ}�~�����ĕ߂炦��B�x�O�ɐ�������͎̂�ɓ����̎��[��J�G���A�g�J�Q�A�w�r�A���Ȃǂ̏�������ߐH����B�s�s���ł͐��S�~�Ȃǂ��H�ׁA�����Ȃǂŕٓ��̒��g�����炤���Ƃ�����̂ŁA���H�Ƃ������A�G�H���̉\���������B�a���m�ۂ��₷���ꏊ��㏸�C���̔������₷���ꏊ�ł͑����̌̂���Ԏp�������邱�Ƃ����邪�A�ґ���s���s�����Ƃ͏��Ȃ��B�˂���Ȃǂł͏W�c�ŌQ�������ĐQ�邱�Ƃ�����B |
|
�@�Y������4-5���ŁA����Ɍ͂�}��ςݏd�˂��������A2-3�̗����Y�ށB���������͖�30���ŁA���͛z�����40���ő����B�C�����ɐ���������̂́A�J�����̌Q��ɍ������ĉa����荇�����Ƃ�����B���܂ɏ��ŁA�J���X�ɂ�����������o�������i�����邱�Ƃ�����A�J���X�Ƃ͂܂�Łu�����̒��v�Ƃ����Ă��������炢�̒��ł���A�߂��Ƀg�r�����邾���ŃJ���X�͏W�c�ł�����������o������A�ǂ��o�����肷�邱�Ƃ�����B����́A�g�r�ƃJ���X�͐H�������Ă��苣���W�ɂ��邽�߂ƍl�����Ă���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�イ�́@�Ƃт͂�����Ɂ@�Ƃт��Ă� |
|
Late autumn, a kite took off to the river
surface. |
|
|
|
|
�g�r / �_�ސ쌧���쒬�_�싴�@2013.11.23 11:56 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2000x1350�j161KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.11.24 /
�ɐ����s������ |
|
��
�ĉH�̏ꍇ�́A�����畠���ɂ����č����H������܂��B�~�H�̏ꍇ�́A�E�Y���ƌ��ԈႦ��قǗǂ����Ă���܂��B�@�i�O�o�Fyatyo19.htm
200�@yatyo22.htm
259�j |
|
 |
|
���i�O���i�����A�p��Pacific
Golden Plover�A�w���FPluvialis fulva�j�F�`�h���ڃ`�h���Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B�V�x���A�ƃA���X�J�����̃c���h���ŔɐB���A�~�G�͓���A�W�A��I�[�X�g�����A�A�C���h�A�A�t���J�����Ȃǂɓn��z�~����B���{�ւ͗����Ƃ��ďt�ƏH�̓n��̎����ɑS���ɔ���B�{�B�̒����ȓ�̒n��ł��A�z�~����̂�����B�쐼�����⏬�}�������ł́A���ʂɉz�~���Ă���B |
|
�@�S����24cm�B���Y���F�B�����ĉH�́A�炩�畠�܂ł̉������������A���̏㕔�ɔ�������肪����B�w�ʂ͉����F�ƍ����F�̔��͗l�ɂȂ��Ă���B�����~�H�́A�̉��ʂ��W�����F�ŕ��������F�����������F�ł���B�{�͍��F�B���͊D�F�݂����т����F�ł���B�c���͐����̓~�H�Ǝ��Ă��邪�A�S�̂ɉ����F�݂��������̉��ʂ������ۂ��B |
|
�@�ɐB���͋ɒn�̃c���h���ɐ������A6���`8���ɔɐB����B�����Ő������A�꒣������B���͒n��ɍ��A�Y�����͕���4���ł���B�H���͎�ɓ����H�ŁA�����ނ�b�k�ނȂǂ�ߐH����B������c�ނŐA���̎�q�����ނ��Ƃ�����B�n��̎�����z�~���ɂ́A���c����A������͌��A�͌��Ȃǂɐ�������B�̌^�̎��Ă���_�C�[���Ɣ�ׂ�ƁA��⊣���������D�ތX��������B���ɁA�z�~�n�ł͊�����͌������A��������̎Ő��Ȃǂ̕��ł悭�ώ@����Ă���B���Ă��Ȃ���u�s���s���[�v�u�L�r���[�v�Ȃǂ̐��Ŗ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
���i�O���~�H /
�ɐ����s�������@2013.11.24
12:10 |
|

|
|
�g��ʐ^�i1800x1200�j687KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.01 / �Y���s |
|
��
���E�I�ɕ��z���钹�ŁA���{�ł͉ċG�ɖk�C���i�Ē��j�A�{�B�A��B�ŔɐB���A�~�G�ɂȂ�Ɩ{�B�ȓ�ʼnz�~���܂��B��ɊC����ނ��a�ɂ��Ă���悤�ł��B�@�i�O�o�Fyatyo7.htm
69�j |
|
 |
|
�I�I�o���i���\�@�w���FFulica atra �j�F�c���ڃN�C�i�Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B�̒���40�p�قǂŁA�o������T�傫���B�����̂��炾�͍����H�тɂ������邪�A�w���̉H�т͐��A��������т�B�z�ɂ͂����������������悤�ȁu�z�v������A�z�Ƃ������͂������s���N�F�B���Ƒ��̎w�̓o�����Z���A�Ђ�̂悤�ȓƓ��̐������u�ّ��v�����B�ĉH�ł͑��̐F�����F���ۂ����A�~�H�ł͊D�F���ۂ��Ȃ�B�c���͂��炾�̉H�тɌ��Ȃ��B |
|
�@���[���b�p�ƃA�t���J�k���A�A�W�A�A�I�Z�A�j�A�ɍL�����z���邪�A�����A�W�A�ȂǂŔɐB�������͓̂~�ɂ͒g�n�ֈړ�����B���{�ł͖k���{�ł͉Ē������A���k�n���암����͗����ƂȂ�B���{�ł́A�����p�������̓���Ƃ��ꂽ���������������A����20�N��������͐����Ɋg�債�A���i�Ȃǂł͖��N���S�H�̌Q���݂���悤�ɂȂ����B����ɂ��̈ꕔ�͔ɐB�����Ă���B |
|
�@�Ώ��A��A���c�A���n�Ȃǂɐ������邪�A�����̒r�Ȃǂɂ��������邱�Ƃ�����B�ّ������܂��g���ăo���������ɉj���A�ނ��됅�ӂ�������Ƃ̕������Ȃ��B�H���͎G�H���ŁA�����A�b�k�ށA�A���̎�Ȃǂ��낢��Ȃ��̂�H�ׂ�B�ɐB���ɂ͂Ȃ��ӎ��������A���̌̂��Ȃ��ɐN������Ƒ��Ƃ��������ӂ���Č������ǂ����Ă�B���̈���Ŕ�ɐB���ɂ͌Q������鐫���������Ȃ�A������������r�ł͐���H���̑�Q�ɂȂ邱�Ƃ�����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�I�I�o�� /
�Y���s�@2013.12.01 12:29 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1600�j496KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.01 /
��z�s�ɍ��� �i���o�j |
|
��
�R�E�m�g���ڃT�M�Ȃɑ����钹�ł���A���E���Ŗ�1000�H�Ƌɂ߂ĊA���Ɋ֓��n���ł͑������邱�Ǝ��̂�����Ƃ����Ă��܂��B�T���ɂ͑�����ɂ������悤�ł����A�ɍ����ɂ�47�N�Ԃ�̔����������ŁA���J���ԑ؍݂��܂����B |
|
 |
|
�w���T�M�i�͍�A�w���FPlatalea leucorodia�j�F�R�E�m�g���ڃg�L�Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B���[���V�A�嗤�����ƃC���h�ŔɐB����B���[���b�p�����ɂ��ɐB�n���_�݂��Ă���B�~�G�̓A�t���J�A�y���V���p���݂���C���h�ɂ����Ă̒n��⒆���암�ɓn��������Ȃ��z�~����B�C���h��ł͗����Ƃ��Ď��N������B���{�ł͐����Ȃ��~���Ƃ��āA�k�C������쐼�����܂Ŋe�n�ŋL�^������B��B�ł͐��͏��Ȃ����A���N����B |
|
�@�̒��͖�85cm�B���J���͖�125cm�B�V���T�M�ނɎ��Ă��邪�A�_�C�T�M�����Z�������������ߊ��Ɍ�����B�S�g�̉H�т������B�ĉH�ł͍A�⋹�����F�݂�тсA�㓪���ɉ��F�̊��H���������B�~�H�ł͊��H���Z���Ȃ�B�{��̓����ł��邭�����͍����Ē����A��[���ւ�^�����Ă���B���ꂪ���O�̗R���ɂ��Ȃ��Ă���B�{�̐�[���͉��F�B���͍����B���Y���F�����A�Y�̕������傫���B |
|
�@
��ɐB���ɂ́A�Ώ��A�͐�A���n�A���c�A�����Ȃǂɐ�������B�z�~�n�ł͏��K�͂ȌQ��ōs�����Ă��邱�Ƃ������B�ɐB���́A�����̌Ώ���͐�Ƃ��̎��ӂ̗тɐ�������B
�����R���j�[���`������B�H���͓����H�B�����␅�c�A���n�Ȃǂł������𐅂ɂ��č��E�ɐU��A�������ɐG�ꂽ���A�J�G���A�J�j�Ȃǂ�ߐH����B�ɐB�`�Ԃ͗����B�n������Ɏ�Ɍ͂�}��p���ĎM�^�̑������A3-4�����Y�ށB���Y�ŕ����A�琗����B�������Ԃ�22-24���ł���B�����̓t�[
�t�[�A�E�t�[�ȂǁB�������������͎̂�ɔɐB���ŁA���{�Ŗ�����������邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�w���T�M�y1/2�z /
��z�s�ɍ����@2013.12.07
14:04 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1750�j354KB
|
|
|
|
|
�w���T�M�y2/2�z /
��z�s�ɍ����@2013.12.07
14:10 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1750�j354KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.15 /
�s���^�� |
|
�� �؉A�ɉB��ċx��ł���܂������A�����ɋ������悤�ň�Ăɏo�Ă��������B�e���܂����B�Y�U�H�A���X�R�H�̌Q��ł������A���̌㐔���������悤�ł��B
�i�O�o�Fyatyo8.htm
72�@yatyo22.htm
253 yatyo23.htm
270�j |
|
 |
|
�I�V�h���i����F�w��Aix galericulata�j
�F�J���ځE�J���ȁE�J�����Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B�I�X�̐������N�₩�ȉH�F�������ƂŒm���Ă���B���������ǂ݂��āu�����v�ƌĂԂ��Ƃ�����B�u���v�̓I�X�A�u��v�̓��X�̃I�V�h�����w���B |
|
�@�̒���45cm�قǂŁA�J���X�ƃn�g�̒��Ԃ̑傫���B�ɐB���̃I�X�͂������̃s���N�A�ڂ̏ォ�犥�H�ɂ����Ă̔��A��ɂ��钷�����F�̉H�A�ÐF�̋��A��F�̗��A���̕��؉H���ό`�����u��ljH�v�Ȃǔ��ɓ����I�ȉH�F�����Ă���B���X�͑S�̓I�ɊD���F�ŁA�ڂ̂܂��ɔ����A�C�����O������A�ڂ̌��ɔ������������B�I�X�͔�ɐB���Ƀ��X�Ƃ悭�����H�F�i�G�N���v�X�j�ɂȂ邪�A�������̃s���N���c��̂ŋ�ʂł���B�I�X�E���X�Ƃ����͔����A�r�͉��F�����Ă���B |
|
�@��ɐB���͌Q��Ő������A�R�n�̌k���A�A�r�A�_���ȂǂŌ�����B������A���̎�q�A�����Ȃǂ�H�ׂ邪�A���Ƀh���O�����D��ŐH�ׂ�̂����̃J���ނƈقȂ�����ł���B�ɐB����5�`6�����ŁA���Ӌ߂��̐X�тŔɐB����B�n�ʂɑ��鑼�̑����̃J���ނƈقȂ�A�����ʼnc������B |
|
�@�I�V�h���͒��̂悢�v�w�̏ے��Ƃ��Ĉ����u�����ǂ�v�w�v�Ƃ������t������قǂ����A�q��Ă͑��̃J���ނƓ��������X���s���A�ɐB�����Ƃɕʂ̑���ƌ����B�ɐB���ȊO�ł̓I�X�ƃ��X�͕ʍs���ł���B��N���ƂɃI�X�̓p�[�g�i�[��ւ���̂ŁA�g���Ɏg����قǒ��������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�I�V�h�� /
�s���^���@2013.12.15
13:32 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1800�j1.28MB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.21 / �����s�����搅������ �i���o�j |
|
��
�W�����̊��A���[���b�p����V�x���A�i�o�C�J���j�܂ł̒n��ŔɐB���A�~�G�ɂȂ�ƃA�t���J�嗤�k���A���ߓ��A�C���h�A���������Ȃǂ֓쉺���A���{�ł͓~�G�ɉz�~�̂��ߔ��i�~���j�A�k�C���ł͏������ɐB���܂��B |
|
 |
|
�z�V�n�W���i���H���AAythya
ferina�j�F�����E�ҍ������咹�j�J���ڃJ���ȃn�W�����ɕ��ނ���钹�ށB���[���b�p����V�x���A�i�o�C�J���j�܂ł̒n��ŔɐB���A�~�G�ɂȂ�ƃA�t���J�嗤�k���A���ߓ��A�C���h�A���ؐl�����a�������Ȃǂ֓쉺���z�~����B���{�ł͓~�G�ɉz�~�̂��ߔ��i�~���j�A�k�C���ł͏������ɐB����B |
|
�@�S��42-49cm�B�����I�X20.7-22.4cm�A���X20.1-21.2cm�B���J��72-82cm�B�̏d0.5-1.3kg�B����������オ��A�������O�p�`�ɂ݂���B�{�͍����A�D�F�̑і͗l������B�I�X�̓��ʂ͐Ԃ��B�ɐB���̃I�X�͓��������̉H�߂��Ԋ��F�A�����̉H�߂���H���키�H�сi������A�������j�͍����B�̑��ʂ̉H�߂͊D�F���A���⍕���F�ׂ̍����Ȗ͗l������B���X�̓��ʂ͊��F�B���X�͓������狹���ɂ����ẲH�߂����F�B |
|
�@�Ώ��A�͐��A�͌��A���p�Ȃǂɐ�������B�H���͐A���H�X���̎G�H��[4]�A��q�A�t�A��A�n���s�A���ށA�����ނ₻�̗c���A�����A�b�k�ށA��̓����A�`�����Ȃǂ�H�ׂ�B�ɐB�`�Ԃ͗����B���ӂ̃C�O�T��V�̖݂␅�ʂɕ����Ԑ����A���̏�ȂǂɃ��V��ςݏグ���������A8-10�̗����Y�ށB���X�݂̂��������A�������Ԃ�24-28���B���͛z�����Ă���50-55���Ŕ��Ăł���悤�ɂȂ�Ɨ�����B����1-2�N�Ő����n����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�z�V�n�W�� / �����s�����搅�������@2013.12.21
09:23 |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1600�j444KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.21 / �������� �i���o�j |
|
��
��ɖk�đ嗤�ŔɐB���A�J���u�C�܂œ쉺���ĉz�~���邻�����A�䂪���ɂ͋ɋH�ɔ���Ɖ]���Ă��܂��B���������ɂ͍�N����A�����Ĕ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�X�Y�K�������菬�U��ł��B |
|
 |
|
�R�X�Y�K���i���銛�A�w���FAythya affinis�j�F�J���ڃJ���Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B���O�̗R���́A���^�̃X�Y�K���̈ӁB�k�A�����J�嗤�k���i�A���X�J�A�J�i�_�j�ŔɐB���A�~�G�͖k�A�����J�������璆���A�����J�A�J���u�C�̓��ׂɓn��z�~����B���{�ł͖����Ƃ��ē~�G�A�k�C���A�{�錧�A�����s�A�_�ސ쌧�A���m���ȂǂŋL�^����Ă���B |
|
�@
�̒���42cm�B�X�Y�K���Ɏ��Ă��邪���菬�����B�Y�����͓������狹�A��������A�������������A�w���͔����B���͑S�̂ɍ����F�ł���B�{�͐D�F�Ő�[�����킸���ɍ����B�����������ōł�����オ���Ă���A��������㓪�ɂ����Čy���i������悤�Ɍ�����B |
|
�@
�Ώ��A�r�A�͐�A�͌��A���p�ɐ�������B�X�Y�K���Ɣ�ׂ�ƒW������D�ތX��������B�H���͂�⓮���H�̌X���̋����G�H�B�ɐB�`�Ԃ͗����B�������̌Ώ��݂̊����◣�ꂽ���ނ�ɉc�����邱�Ƃ������B���ʏ�ɕ��������������A�A�W�T�V�ނ̃R���j�[�̒��ɉc�����邱�Ƃ�����B1��8-10�̗����Y�ށB�������Ԃ�23-25���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�R�X�Y�K�� / ���������@2013.12.21
12:55 |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2000x1235�j517KB
|
|
|
|
|
|
|

|
|
�E�B�L�y�f�B�A�t���[�S�Ȏ��T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.22 / �͌��t�B�[���h�Z���^�[ |
��
��̏�ɋ���p���B�e�����������̂ł����A�Ȃ��Ȃ��v���ʂ�ɂ͍s���܂���ł����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�O�o�Fyatyo1.htm
4�@yatyo16.htm
152
yatyo21.htm
231�j |
|
 |
|
�����r�^�L�i�ڗ��O�@�w���FTarsiger cyanurus
�j�F�����E�ҍ������咹�j�X�Y���ڃc�O�~�Ȃɕ��ނ���钹�B�ċG�̓��[���V�A�嗤�̈����т�q�}�����R���ŔɐB���A�~�G�̓��[���V�A�嗤�암�ʼnz�~����B���{�ł͉ċG�ɖ{�B�A�l���̈����R�тŔɐB���A�~�G�͕W���̒Ⴂ�ꏊ�։����i�����j�B�S��14cm�B���H�̉H�т͐��B�̑��ʂ̉H�т̓I�����W�F�ŁA�p���iflanked���e���A���ʁj�̗R���ɂȂ��Ă���B���ʂ̉H�т͔����B�����i����Q�N�j�ɂȂ�ƃI�X�̔w�ʂ̉H�т͐��A�c����X�̔w�ʂ̉H�т͊��F�B�포��cyanurus�́u���v�̈ӁB |
|
|
|
|
|
|
|
�����r�^�L /
�͌��t�B�[���h�Z���^�[�@2013.12.22 13:25
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1150x1200�j227KB
|
|
|
|
|
�s���̐X�̃����r�^�L / ���l�s�@2011.01.17
12:56 |
|
|

|
|
�g��ʐ^�i1600x1200�j241KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.28 / ���i�_�ސ쌧�j |
|
��
��ϐ_�o���ŁA�Ȃ��Ȃ��߂��ł̎B�e�������Ă���܂���B�����_���Ă�������ɁA����T���Ȃ���j���ł��Ċ���グ����A�C�t����Ĕ��Ă��܂��܂����B�i�O�o�Fyatyo8.htm
73�@yatyo21.htm
244�j |
|
 |
|
�J���A�C�T�i��H���A�w���FMergus
merganser�j�F�J���ڃJ���Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��B���[���V�A�嗤���k���Ɩk�A�����J�k���ŔɐB���A�~�G�̓��[���b�p�A�����A�W�A�A�C���h�����A���������A���N�����A�k�A�����J�����Ȃǂɓn��z�~����B���{�ւ͓~���Ƃ��ċ�B�Ȗk�ɓn�����邪�A�k���{�̕����n�����������B�k�C���ł͗����Ƃ��ď������ɐB���Ă���B |
|
�@�J���ނ̒��ł́A�ł��ג���������i�̍��Ƒ̒��̔䗦�j��̈�B�S���̓I�X�ŊT��68cm���x�B���X�̓I�X��肩�Ȃ菬�������ϒl��60cm���x�B�I�X�́A�������ΐF����̂��鍕�F�ŁA���H�͂Ȃ����㓪�����ӂ����Ō�����B��e�E���y�щ��ʂƔw�⏬�J���E�O�ؓ��͔����B�w�̏�ʂ͍����B���X�͓����������F�ŁA���H�͒Z���B������̂̉��ʂ͔��F�ŁA�w����̑̂̏�ʂ͊D���F�ł���B���Y�Ƃ��{�Ƒ��͐Ԃ��B |
|
�@�z�~���́A�a���̂Ƃ���Ώ��A�͐�Ȃǂ̒W����ɐ������邪�A���p�≈�ݕ��̐ɂ��������Ă���B�k���{�ł͊C����ɑ����������A�����{�ł͒W����ɑ�����������X��������B���܂�傫�ȌQ��͍�炸�A1-���H�̏��Q�Ő�������B�ɐB���́A�����̌Ώ��̎��ӂ̑����⎼�n�ɐ�������B�H���͎�ɓ����H�B�������ċ��ނ�ߐH���邪�A�x�O�̌����ɐ�������̂̒��ɂ͐l�Ԃ��^����p���Ȃǂ�H�ׂĂ�����̂�����B�ɐB�`�Ԃ͗����B�ɐB����4-6���ŁA�n��Ɍ͂ꑐ�Ȃǂ�p���ĎM��̑�����邪�A�����𗘗p���邱�Ƃ�����B�����A�琗�͎����s���B�����́A�J�����A�J�����B |
|
|
|
|
|
|
|
�J���A�C�T /
���i�_�ސ쌧�j�@2013.12.28 11:12
|
|

|
|
�g��ʐ^�i2400x1550�j638KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.29 / �Y���s |
|
��
�������J�b�v�����O���n�܂����悤�ŁA���r�܂��������d�������Ă���܂����B
�i�O�o�Fyatyo12.htm
116�j |
|
 |
|
�I�i�K�K���F�J���� �J���� �S���i���J���j�Y
61-76cm�@��
51-57cm�i80-95cm�j�B�Y�͑̂��D�F�ōׂ����͗l������B���̓`���R���[�g�F�A���̌�납���A���͔��F�B���͔����B�K�A�e�i�킫�j�͒W���F�A�������͍��F�B���H�̒���2�������F�Œ����B�{�͏�ʂ͍������ʂ͐D�F�B���͊D���F�B�G�N���v�X*�͚{�̗������D�F�Ȃ̂ŋ�ʂł���B���͑S�̂����F�ō����F�̔��䂪�S�g�ɂ���B��͊��F�����Ă���B�������͔����B���������B�V�C�[�V�C�[���A�v���b�v���b�Ƃ������Ŗ��B |
|
�@��Ԃɐ��c�⎼�n�ɏo�č̉a����B�r�ȂǂŚ{�𐅂ɂ��ē������A�����Ƃ��ĐH�ׂ�B�t�������Ď�����Đ���̑͐ϕ������ށB���̃J���ނ�蒷����������Ă��邽�߁A�[������𗘗p�ł��邪�A�����ɐ����č̉a���邱�Ƃ͂Ȃ��B�G�H���ŁA�����̎�q��j�ЁA���������Ȃǂ�H�ׂ�B�a�t��������Ă���p���悭�ڂɂ���B
�ɐB������5�`7���ň�v��Ȃł���Ԃ͕������ɉ��������B |
|
*�G�N���v�X�F�J���ނ̗Y���ɐB���o�ߌ�A�ꎞ�I�Ɏ��̂悤�Ȓn���ȉH�F�ɂȂ��ԁB |
|
|
|
|
|
|
|
|
�I�i�K�K�� / �Y���s�@2013.12.29
14:17 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2000x1333�j366KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.31 / �Y���s
�i���o�j |
|
�@�k���[���b�p����V�x���A�A�J���`���c�J�܂ł̃c���h���ȓ�̐X�сA��̓E�X���[�ŔɐB���邻���ŁA�䂪���ւ͓~���Ƃ��ēn�����܂��B�k���{�ɑ����n�����A�{�B�����ȓ�Ŋώ@�����̂͑����Ȃ������ł��B�R���Ƀz�I�W���K�������Ă���Ɖ]�����āA�B�e�ɍs���܂������A�c�O�Ȃ��牓���Ăǂ��ɂ��Ȃ�܂���ł����B11���ɏ��M�`�ŎB�e�o���܂����B��30m�Ɣ�r�I�߂������̂ł����A���z���x�����������������A�����̗ΐF�����\���F���o�Ȃ������̂��c�O�ł����B12���ɂȂ�A���N�̓z�I�W���K�����勓���Ă���Ă����悤�ŁA�Y�����킹���30�H�ȏア��Ƃ̂��Ƃł����B |
|
 |
|
�z�I�W���K���i�j�����A�w���FBucephala clangula�j�F�J���ڃJ���Ȃɕ��ނ���钹�ނ̈��ł���B�a���̗R���́A�j�ɔ����͗l�����邱�Ƃɂ��B�B�w���̓��A����Bucephala�̓A���N�T���h���X3���i�剤�j�̔n�̖��O�������ꂽ���̂ŁA�포��clangula�́u�₩�܂��������v���Ƃ��Ӗ�����B |
|
�@�k���[���b�p����V�x���A�A�J���`���c�J�܂ł̃c���h���ȓ�̐X�сA��̓E�X���[�ŔɐB���A�n���C��y���V�A�p�A���{�A�����암�A���N�����Ȃǂʼnz�~���鋌�k�戟��ƁA�A���X�J��J�i�_�ŔɐB���A�A�����J�����Ȃǂʼnz�~����V�k�戟��ɕ�������B���{�ւ͈���z�I�W���K�����~���Ƃ��ēn������B�k���{�ɑ����n�����A�{�B�����ȓ�Ŋώ@�����̂͑����Ȃ��B |
|
�@�S���̓I�X�Ŗ�46cm�B���Y�Ƃ����̃J���ނƔ�ׂāA�̂̊���ɓ������傫��������B�Y�͓������ΐF�̌���̂��鍕�F�ŁA��̑O�ʂɊۂ�����������B�w�͍����A���A���A���H�͔����B���͓����Ɣw�͊��F�ŁA�̉��ʂ͊D���F�B��̔����͂Ȃ��B |
|
�@4������6���ɂ����ĔɐB����B�ɐB���́A�X�ёт̐��Ώ��ɐ�������B�z�~���ɂ͌Q������A���p��`�Ȃǔg�̐Â��ȊC��ɐ�������B�͌�������̌Ώ��ɓ��邱�Ƃ�����B�������čb�k�ނ�C�J�A�L�ނȂǂ̓�̓�����ߐH���邪�A���ނ␅���Ȃǂ��H�ׂ�B�ɐB�`�Ԃ͗����B������n��̌��ȂǂɌ͂ꑐ��H�т�~���ĉc�����A�����ꏊ�ɌJ��Ԃ��c������B1���̎Y������7-11�B�����A�琗�͎����s���B����������27-30���ŁA���͖�60���Őe����Ɨ�����B |
|
�@�Y�͔ɐB���Ɂu�M�[�@�M�b�M�[�v�Ƒ���������u�N�B�@���[�N�v�Ɩ��A���̉H�т��ӂ���܂�����A�����Ȃ��L�����鋁���f�B�X�v���C���s���B�߉���̃L�^�z�I�W���K���Ƃ́A�I�X�̋����f�B�X�v���C�̓������������炩�ɈقȂ��Ă���B���̂������A�{��ƃL�^�z�I�W���K���͕��z�̏d�Ȃ肪����ɂ��ւ�炸�A���R�E�ł̎G��͂̕����킸�������Ȃ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
�z�I�W���K���y1/2�z / �Y���s�@2013.12.31 13:29 |
|

|
|
�g��ʐ^�i2000x1400�j339KB
|
|
|
|
|
�z�I�W���K���y2/2�z / �Y���s�@2013.12.31 13:38 |
|

|
|
�g��ʐ^�i1200x850�j202KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013.12.31 /
�c�����c�� |
|
�� �P�Q���R�P���ɎB�e�����c�����c���́u���V�K���v�ł��B
�����̂Ȃ̂ł����A�ʂ������̌��̌����ŁA����Ȃɕ��͋C���ς��܂����B�i�O�o�Fyatyo16.htm
160�j |
|
 |
|
���V�K���i�����AAnas falcata�j�F���ؐl�����a���k�����A�����S���A�E�X���[�A�V�x���A�ȂǂŔɐB���A�~�G�ɂȂ�Ɠ���A�W�A�A���N�����A���ؐl�����a���암�Ȃǂ֓쉺���z�~����B���{�ł͓~�G�ɉz�~�̂��ߔ��A�k�C���ł͏������ɐB����B�����E�ҍ������咹�j�J���ڃJ���ȃ}�K�����ɕ��ނ���钹�ށB |
|
�@�ɐB���̃I�X�͊z����㓪�A���A�j�̉H�߂��Ԏ��A�Ⴉ��㓪�̉H�߂��ΐF�B�A�̉H�߂͔���W���F�ŁA������֏�̔��䂪����B���H��̉��ʂ�키�H�сi�������j�͍����A���̑��ʂɂ͎O�p�`�̉��F�����䂪����B�O�͒����p�Ȃ��A�����H�т̊O���i�H���j�������B |
|
�@�͐�A�Ώ��Ȃǂɐ������A�~�G�ɂȂ�Ɠ��p�Ȃǂɂ���������B�H���͎�ɐA���H�ŁA��q�A�����A���A�C���Ȃǂ�H�ׂ�B�ɐB�`�Ԃ͗����B6-8���ɐ��ӂ̖݂ȂǂɌ͂ꑐ��g�ݍ��킹���������A6-9�̗����Y�ށB���X���������A�������Ԃ�24-25���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
���V�K���y1/2�z
/ �c�����c���@2013.12.31
10:48:56 |
|

|
|
�g��ʐ^�i1600x1125�j206KB
|
|
|
|
|
���V�K���y2/2�z
/ �c�����c���@2013.12.31
10:49:22 |
|

|
|
�g��ʐ^�i1800x1300�j311KB
|
|
|
|
|
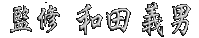
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�B�e �E���� �F |
���R ��
|
|
�@ |
|
 |
���ւ芽�}�I |
|
|
|
|
�y�o�g�n�z �L�����{���s�㉺��
�y�a�����z ���a22�N�R��
�y���Z���z ���l�s�˒ˋ�
�y�� �@���z (1) ���|�i�ǂ�����̂���쐶���j |
|
|
|
|
(2) �ԍD���������Ē��A���͎B�e���ɂ߂ē�����ǖԂ������ƂɁB�f�W�J���̏o���ŁA ���߂ĎB�e���J�n��
�܂����B���̓����A���̎ʐ^���f�ڂ������ł��ˁB
(3) ���@�̎B�e���s������ŁA���R�J���Z�~�̑�������̏�i�ɑ����������Ƃ���A���ł́A�������菬����
�B�e�ɛƂ��Ă���܂��B�V���b�^�[�������u�Ԃْ̋����͉����ł��B |
|
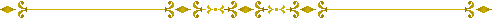 |
|
|
�@�{�i�I�ɒ��̎B�e���n�߂ĂX�N�o�ߒv���܂����B�J�������Ƃ��Ƃ��V��ڂɂȂ�܂����B���߂̂���͎p���B�e���邾���Ŗ������Ă���܂������A�i�X�Ɣ�т��̂ȂǓ����̂���p��ǂ�����������������ڂ��Ă���̂������ł��B
�@����25�N�́A�Ȃ���������������A�S�ĂɑΉ��ł����킯�ł͂���܂��A�����E���B�肪 �S�����߂Ă��܂��B�ď�͑̒��s�ǂ�����A���x�{���܂�������A�����g�̒��^�Ƃ������A�����̂̍s���ɂ��ٕς�����̂�������܂���B
�@
|
|
|
�@
�@��{�I�Ɏʐ^�B�e�ł������Y��Ȏʐ^�ɂ��Ȃ���Ȃ炸�A�����Y��Ȓ���ǂ��|���邱�ƂɂȂ�܂����A���ꂾ���Y��Ȓ��Ƒ����o�����Ɖ]�����ƂȂ̂ł��傤�B
�@�ߊԂɋ��钹�͖w��ǎB�e�ς݂ɂȂ�܂�������A�V�����W�I�����߂ĉ������邱�ƂɂȂ�܂����A���̍ۂ͎Ԃ̉^�]�Ȃǂ̋��͂������������Ԃ�����Ƃ������Ƃ��d�v�ł������łȂ��A�ƂĂ���Ȃ��ƂŁA���X���ӁX�X�ł��B
�@2014�N�����C�ŎB�e�s���o����l�A�̒��Ǘ��Ə����W�ɐS�|�������Ǝv���܂��B���Ē����邱�Ƃ���݂ɂȂ�܂��B�F���܂̂����N���F�O�������܂��B�L��������܂����B |
|
�������c |
|
�����ʐ^�W�q ��193�W �r�u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v |
|
�B�e�E����F���R ���@�@�ďC�F�a�c�`�j |
�@ ����26�N�i2014�j2��17�� ��i�F��4�� �摜�F91�i��89+��2�j �Ő��F5 �t�@�C�����F190 �t�@�C���e�ʁF51MB
����12�N�i2000�j�`����26�N�i2014�j�@��i���F467�@�Ő��F1,900�@�t�@�C�����F86,515 �t�@�C���e�ʁF17,311MB |
|
|
|
|
|
|
| ��̓��G�]�t�N���E�͖��̒��@�@�k�M |
|
|
�䂫�̂ق�@�����ӂ��낤�́@��߂̂Ȃ� |
|
A snow cave, the Ural Owl in a dream. |
|
|
�y�ҏW�q���I�Ԗ���z |
�G�]�t�N���E /
�D�y�s�~�R�����@2013.02.23
11:21 |
|
![�G�]�t�N���E / �D�y�s�~�R�����@2013.02.23 11:21](images10/yatyo393.jpg)
|
|
�g��ʐ^�i2000x1750�j630KB
|
|
|
|
|
|
|
|
����̖쒹�V���[�Y�I
|
|
�@�{���A�����ʐ^�W���l�E���R������̑�Z��ƂȂ�u�쒹���B�闷'�P�R�v�����������B2005�N�X��19�����l�s�˒ˋ救�������̃J���Z�~�ȗ��A2013�N12��31���c�����c���̃��V�K���܂ŁA�쒹���B�闷�͊��ɂW�N�R�����ƂȂ�A�B�e�����V�[����367�ɒB�����B |
 |
�@ |
|
�@internet���������Ă��A�l�ł��ꂾ�������̖쒹�\���Ă���l�͌������炸�A�u�p���͗͂Ȃ�v�̌��ǂ����A����Ƃ���������{��̖쒹�V���[�Y�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���Ɋ�����B |
|
�@���R����͂���܂ł̉掿�ɖO�����炸�A�f�W�J�����V��ڂƂȂ��A�ŐV�̃����Y�ƃ{�f�B����g���ăv�����݂̃N�I���e�B��Nj����Ă�����B�������A�P���Y��ɎB�ꂽ�����ł͖����ł����A����ߊl�����u�ԂȂǁA�����̂���ɂ߂ē���V�[�������ׂ��A�r���Ă�����B |
|
|
�@�������Ȃ�̖������A�b�v���Ă���̂ŁA���o�͂Ȃ��Ȃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă������A2013�N�́A74����30�������o�������BGoogle
�̂��A���AWa��Da�t�H�g�M�������[�̃T�C�g���������u���ɂł���̂��A�����A�쒹�V���[�Y�S�ł̃g�b�v�Ɍ����{�b�N�X��݂��A����܂ł̌f�ڗ������u���ɔc���ł���悤�ɂ����B�܂��u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v�ł́A�O�o�̍�i���������A�e���ɃT�C�g�������N��ݒ肵���B
�@ |
|
|
�@
�@���R����̃��C�t���[�N�ɂӂ��킵���X�P�[���Ɠ��e�������̊������́A���ꂩ����X�ɃR���e���c��lj����A���N�A��N�Ԃ̐��ʂ��I�����Ē��������B�S���𗷂��Ė쒹�̃��}���Ɗ�����ǂ��������鉡�R����̏�M�ƔE�ϋ��������ɐS���犴�Ӑ\���グ��ƂƂ��ɁA�쒹�̃��}���Ɗ����������ɐ���{�i�h�J�����}���Ƃ��āA2014�N���v�X�̂�������F�O�\���グ�܂��B�L���������܂����I
�q �q �r
2014.02.17 �ďC �a�c�`�j |
|
|
|
|
|
| �������̏t�̑�����剎�q�@�@�k�M |
|
|
������̂́@�͂�̂��Ԃ���@�����܂��� |
|
A breath of spring, a rosefinch at Akiruno. |
|
|
�y�ҏW�q���I�Ԗ���z |
|
|

|
|
�g��ʐ^/�`���E�T�M�i2400x1600�j486KB |
|
2014�N2��17���i���j���@ �i�c�S���q
�@�l���@�@ ���s�s����̂��ւ�
Re: �{�N��S�W�u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v�����I�@�����́B�@������@���Ղ�̉f�����R�����蒸���܂��ėL��������܂����B���@����ɂ͂ƂĂ������̂���@�쒹�̉f����L��������܂��B�����ȂǕ��i�����@��̂Ȃ����̐��@�p�@�������y���݂ɂ��ā@�������q�������Ē����܂��B�~�̒��͊��ׂōς܂��Ă��܂����@���낢��Ȍ`��������@�{���ɂ��������f���ł��B�L��������܂��B�@���N���ǂ����@��낵�����肢�v���܂��B
| �����́B���v���Ԃ�ł��B���ւ肠�肪�Ƃ��������܂����B���R����̂��A�ŁA���i����ɂ���쒹���������邱�Ƃ��ł��A���g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�{���ɐ��E��������{�ɖ쒹������Ă����ł��ˁB���̃��}���Ɗ�����o���Z�̂ɉr�ݍ���ł��������B���ꂩ����ǂ����X�������肢���܂��B�L���������܂����B |
|
2014�N2��17���i���j���@ H. K.
�@�l����@�@ �����s����̂��ւ�
Re: �{�N��S�W�u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v�����I�@�����͂�����̐�͔@���ł����H��������\�����ʐϐ�ɑ����ł����B�X�R�b�v����������~���̓����Ȃ�����܂����B���g�Ȓn�ɏZ�݁@�m�z�z���Ƃ��ċ����̂��ˑR�̐�ɉ�������ꂽ�l�Ɏv���܂��B�_���̑�C�Ɠ����Ă��鎖���v���Α��ꂮ�炢�̐�ő����łȂ��ƌ���ꑊ�ł��@�쒹�̗��A�L��@���x���Ă������ł��ˁ@���̂Ȃ����������ċ���̂͑f���炵���Ǝv���܂����@�L�������܂����B
�����́B���������ő�ς�������ł��ˁB�����ȏ�ɂ���J���ꂽ�����m��܂���B�i�j������������ɐႪ�c���Ă��āA��ςł��B���T�̌㔼�ɂ͂܂��Ⴊ�~��Ƃ̗\��ł��B���������̂ł��ˁB
���X�Ɂu���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v���������������A���h�ł��B���C�ɂ����Ċ������ł��B���ꂩ����X�������肢���܂��B�L���������܂����B |
|
2014�N2��17���i���j���@ �ؑ� ��
�@�l����@�@ ���{�哌�s����̂��ւ�
���肪�Ƃ��������܂��B�@�a�c�l�A�������������܂��B���X���{�̍Ղ�ɂ��Ă��z�M�����܂��ėL��������܂��B
����͂܂��A���{�̖쒹�̎ʐ^�W�����z�M�����܂��ėL��������܂��B���炵�������̎p�̎ʐ^�ɖ�����Ă��鎟��ł������܂��B
���l�̎��ł͂������܂����A���̘A���̊����ɐk���������Ă���܂��B��N�Ȃ����������ɂ���܂��A�~�ь����Ȃǂɏo�|����̂������̎��Ȃ̂ł����A���N�͈�w�o�s���ɂȂ�A�Ƃ��Ă��Ă��鎟��ł��B�i�j
������v�X������̏�A�f���炵���ʐ^�W�̔z�M�����҂����Ă��܂��B�����������܁A���̂��������������܂��悤�B
���͂悤�������܂��B���X�Ɂu���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v���������������A�L���������܂����B�u�p���͗͂Ȃ�v�ŁA�쒹�V���[�Y���U��𐔂��A�v�X���e���[�����Ă��܂����B���������悤�ɁA���x���Ă�������܂��ˁB
�����́A��T�ɂ킽���đ��ƂȂ�A�[���̑����쌒�N�E�H�[�N���ł����A���ւɕ��������Ă��閈���ł��B����̓y�j���ɍL���̗��Ղ���ނ���\��ł������A�_�C��������A��ނȂ����~���܂����B
���̂��A�ŁA�x�����Ă���ҏW���͂��ǂ�A�A���A�\�`�I�����s�b�N�̎������p���f�B�X�v���[�̍����Ō��Ȃ��犴���V�[���̕ҏW�𑱂��Ă��܂��B�i�j
�������ő�ςł��ˁB�]��ʼn�������Ă͌����q������܂���̂ŁA�ǂ����������̏�A�����C�ł��߂����������B�L���������܂����B |
|
2014�N2��17���i���j���@ ���[�����O���X�g�o�^�ҁi��400���j�@�@�l�@�@Wa��Da�t�H�g�M�������[���
�{�N��S�W�u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v�����I�@���ӂ́B�����قǖ{�N��S�W�A2000�N�V������̒ʎZ��467�W�ƂȂ��i���A�b�v���܂����B�i�ʐ^�Y�t�j
�����ʐ^�W�q ��193�W �r�u���{�̖쒹���B�闷'�P�R�v
http://wadaphoto.jp/kikou/yatyo25.htm
�B�e�E���� �F ���R ���@�@�ďC�F�a�c�`�j
���̍�i�́A��N1�N�ԁA���{�𗷂��Ė쒹���B�e���ꂽ���R����̖쒹�V���[�Y��Z�e�ŁA�T��91���̊������ł��B
�쒹�̃��}���Ɗ��������߂đS���𗷂����W�N�R�����ɐ������V�[����376���ƂȂ�A���{��̖쒹�V���[�Y���X�Ȃ銮���x�����߂܂����B�ǂ����A�����Ԃ̂���Ƃ��ɁA������Ƃ����������B
��==========================================================��
��== �v�����c���t�H�g�M�������[ url: http://wadaphoto.jp/ ==��
��== mail: master@wadaphoto.jp�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ==��
��== �a�c�`�j ==============================================��
|
