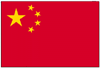|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ツアー三日目の夜は、夕食後、市内の湖を巡るナイトクルーズに出かけた。近年、古くから自然の城濠とされてきた桂林市街を流れる2つの川と4つの湖がひとつに結ばれ、船で航行できるようになった。「水の都」としての一面を持つ桂林の魅力をクルージングで楽しむという趣向で、両江四湖というツアーである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杉湖のナイトクルーズ乗り場 |
|

|
|
拡大写真(1400x960)277KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「両江四湖」とは、漓江、桃花江(とうかこう)と、杉湖(すぎこ)、榕湖(ようこ)、桂湖(けいこ)、木龍湖(もくりゅうこ)で、その合流地に桂林市がある。以前は水が澱んで汚い水溜りだったものを改修し、3年前からライトアップして夜の観光地に仕上げたもの。ライトアップ費用は、一晩で5万元(80万円)かかるという。漓江下りで世界に名を馳せている桂林にまたひとつ素晴らしい夜の観光が加わった。 |
|
|
|
我々は杉湖の船乗り場からチャーターした遊覧船に乗船し、カラフルにライトアップされた夜の湖を巡った。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
記念撮影 |
|

|
|
拡大写真(1400x1050)261KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金銀双塔は、杉湖(すぎこ)の東南に位置するツインタワーで、銅塔(手前)と瑠璃塔(奥)に分かれており、日月双塔とも呼ばれる。銅塔は9層41mの高さで、湖の中に立つタワーとして世界一のタイトルを持つ。瑠璃塔は杉湖の島の上に建ち、7層35mのタワーで、水面下の水族館を介して銅塔と通じている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金銀双塔の夜景 |
|

|
|
拡大写真(1600x1300)288KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四湖に架かる様々な形の橋は、全てライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出している。写真下は、ヨーロッパで見られる橋を取り入れた桂湖の麗澤橋(れいたくきょう)で、遊覧船を入れたナイスショット。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
幻想的な桂湖の麗澤橋のライトアップ |
|

|
|
拡大写真(1800x650)147KB |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
広西チワン(壮)族自治区は、歌の神様と讃えられる劉三姐(りゅうさんちぇ)の故郷。二胡(にこ)の哀愁を帯びた美しい調べがキャビンに流れる。観光客は、四湖の夜景を見ながら至福のときを過ごす。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美しい曲を奏でる二胡奏者 |
|

|
|
|
|
|
|
|
| |
中国の民族楽器・二胡(にこ)は、二弦の胡琴(こきん)で、 清朝の中頃より起った中国の弓奏弦楽器である。二弦の擦弦楽器(さつげんがっき)*で、紫檀(したん)などの胴に蛇皮を張り、弓を右手に持ち、弓毛(馬尾毛)を弦と弦の間に挟み、左膝の上に立てて擦奏(さっそう)する。 |
|
| |
*擦弦楽器:バイオリンのように、弓や棒で弦をこする(擦・さつ)ことによって音を出す楽器の総称。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
橋の下を通る遊覧船 |
 |
|
拡大写真(1400x1050)312KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遊覧船が途中で止まると、左舷側で竹排(ツーパイ)(竹筏)に乗った鵜匠が鵜を操って鵜飼を披露してくれた。日本とは違って、鵜にはロープがついておらず、魚を捕らえると舟に戻ってくるように訓練されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
竹排(ツーパイ)(竹筏)の鵜飼 |
|

|
|
拡大写真(1800x1300)277KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
川鵜の首にはロープの代わりに獲物を飲み込まないように紐(ひも)が巻かれている。舳先のランプは、昔夜店で懐かしいカーバイトランプ。注水器を緩めると水滴が落ち、カーバイトが化学反応してアセチレンガスが発生し、火口(ひぐち)から出るガスに点火して発光させる。アセチレンガスの匂いが懐かしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魚を飲み込んだ鵜の嘴の根元をつかむ |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
川鵜が魚を捕まえて戻ってくると、嘴(くちばし)の根元をつかんで口を開け、獲物を吐き出させて魚籠(びく)に入れる。その手際の良さは、プロの匠の領域である。右舷側にも、もう1隻来ていたが、弟子らしく、漁獲は零だったので、簡単そうにみえる技が大変熟練を要するものであることがわかった。素晴らしいアトラクションだった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魚を吐き出させて魚籠に入れる |
|

|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
桂湖に聳える桂湖飯店のライトアップが素晴らしい。中国風の建物の輪郭が浮き上がり、まるで不夜城のよう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美しい桂湖飯店のライトアップ |
 |
|
拡大写真(1600x800)210KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全て純白の大理石で造られたという豪華な榕湖の古榕双橋。うまく湖面に映れば、円形の眼鏡橋が出現する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
豪華な大理石の古榕双橋 |
|

|
|
拡大写真(1600x760)217KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遊覧船は、いよいよ宋城の水門を通過し、木龍(もくりゅう)湖畔に建つ宋城(そうじょう)の地先水面に向かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水門を通過するナイトクルーズ船 |
|

|
|
拡大写真(1800x1180)388KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水門を通過すると、昼間、畳彩山(じょうさいざん)山頂から見た明月峰(めいげつほう)の下を通り、反り橋(そりばし)をくぐると、千年前の宋代の城郭を復元した宋城の前に出る。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
拡大写真(1600x1050)215KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
復元された宋城は、すべてライトアップされ、漆黒の夜空に美しく輝いている。観客たちは、この素晴らしい不夜城に言葉も忘れて見入っていた。後部デッキに立つ私は、ひたすら役に立つとは思えないフラッシュを光らせながら、オリンパスE-330のシャッターを切り続けていた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宋代建築群のライトアップ |
|

|
|
パノラマ写真(2400x1200)401B |
|
|
|
|
|
|
|
|
桂林の旅は、この美しい七重楼閣の夜景とともに終わった。このあと、遊覧船は桂湖の船着場に引き返し、桂山大酒店で最後の夜を過ごしたのち、翌11月19日(日)、復路を無事帰国することができた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美しい七重楼閣 |
|

|
|
拡大写真(1800x1350)311KB |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
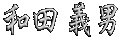
OLYMPUS E-330 E-500
11-22mm
14-54mm
SIGMA 55-200mm
800万画素
2,300枚 3,760MB
撮影 2006年11月16-18日
|
|
|
素晴らしい旅だった。スイスのカラリと晴れた快晴の旅も良かったが、霧のたちこめる漓江下りもまた格別であった。 |
|
中国の少数民族との触れあいも新鮮だった。55の少数民族のうち最大のチワン族がタイ系の人たちであったのも驚きであった。 |
|
中国の広さ、国民の多さと多様さ、そのどれをとっても、日本はその対極にある。それだけに、カルチャー・ギャップもまた大きい。 |
|
日本は、かつては発展途上国で、漢字や仏教や多くの科学文化が中国から伝わった。その中国が今、反対の立場に置かれている。 |
|
|
 |
| 2008年8月、北京で第29回夏季オリンピックが開かれる。中国ではそれに向けて準備が進められているが、外国人が目にする道路や建物は、全て化粧直しがおこなわれるが、見えないところはそのままだという。 |
| 21世紀は中国の時代といわれ、多くの先進国が中国市場に進出し、中国は急速な経済発展を遂げている。その反面、富める者と富まざる者との格差は益々広がりつつあり、日が当たる場所とそうでない場所とのギャップがとても大きい。激しく変革する中国だが、漓江の悠久の流れと少数民族の貧しさは、今も昔も変わらない。 |
| 中国における千円札の値打ちがこれほどまでに高いとは思わなかった。遊覧船に群がる竹筏の人たちや土産物屋の売り子たちは「せんえん」を連呼する。2個千円が最後には30個千円になってしまう。千円札を手にした彼らはきっと満足していると思われるが、中国の現状と苦悩を象徴しているようだ。 2006.12.9 〈 完 〉 |
|
|
|
|
|
|
2006年12月10日(日)晴 池田武久 様より
「霧の桂林紀行」に感動! 今回も素晴らしい写真多謝 私はこの3年間に中国へ13回行きましたが 桂林へは行きたいと思いながらまだ行けていません 何時も何とか良い写真を撮って 御見せしたいと思っていますが 貴方の様にはいかず 残念に思っています
何時も思って居るのですが 貴方は写真だけでなく 音楽にも相当な 造詣をお持ちのようですね そこで御願いがあります 今度の 畳彩に使用されている 中国民謡の 名前を教えていただき できれば譜面を御願いできませんでしょうか では 何位分宜しく御願いします
添付写真は 共に洛陽人民政府の我々を歓迎する唐代の宮廷様式の鼓舞宴です 本年の10月 岡山県が建立した 吉備真備像の 20周年記念イベントに 岡山県知事が公式訪問し 私達県民代表が同行したものです
|
唐代宮廷様式の鼓舞宴/洛陽 2006.10 |
|

|
|
拡大写真(1400x933)314KB |
撮影:池田武久 |
|
|

|
|
拡大写真(1400x933)268KB |
撮影:池田武久 |
|
|
こんにちは。早々に「霧の桂林紀行」をご覧いただき、有り難うございました。ことのほか中国に造詣の深い池田さんのご感想はいかばかりかと思っておりましたが、満足頂けたようで安堵しています。(^^
音楽も気に入って頂いたようで、桂林で購入した3枚のCDが大変役に立ちました。土産店では売っておらず、中国人ガイドも余り音楽のことを知らず、1時間の市内散策を潰して、音楽店を見つけ、漢字が読めることからあとは身振り手振りで劉三姐や二胡大師の名曲を探し出しました。
ご質問の歌は、「采茶姐妹上茶山」で、英語では Tea-picking Sisters Going to the Tea Mountains です。15曲のうちから選んだもので、とても良い歌だと思います。残念ながら譜面は収録されていません。歌を添付します。
素晴らしい写真、有り難うございました。踊り子たちはまるで竜宮城の乙姫様のようですね。早速、紹介させていただきます。有り難うございました。
|
|
2006年12月10日(日)晴 hikari 様より
「霧の桂林紀行」有難う御座います 今日は 「霧の桂林紀行」の完成版、有難う御座います。ご同行中の皆様の状況、写真の中から良く伝わってきます。切り立った断崖、渓谷、水の流れの様子等はまさに桂林を象徴している様です。「睡蓮の花」は
お見事です!
現地ガイドの”陳雲安”さんの説明に有るように今、中国は世界的に一番の経済力の伸びを続けている中、陳さんが懸念されている様に、中国人民のマナーの悪さ等を客観的に捉え、顰蹙を買っている事など自国の恥部を包み隠さず説明されている姿に感動さえ覚えました。それも現地に行き直接ガイドさんの説明を聞くことで、信憑性のある解説が出来ることだと思います(和田さんに感謝!!)。私も近い将来(願いが叶えば)是非一度行ってみたい所です。きょうは有難う御座いました。
|
お便り有り難うございました。「霧の桂林紀行」を気に入っていただき、嬉しく思います。是非、一度足を運ばれることをお勧めします。日本でも中国からやってくる観光客の評判は芳しくありませんが、分かっている人はちゃんといるんですね。
日本も昔、農協の団体旅行客がステテコ姿でホテル内を歩き回ったりして、顰蹙を買いました。それと同じ段階を経て、中国も成熟した国になってゆくのではないでしょうか。
陳さんによると、北京オリンピックに向けて、暑くても裸で道路を歩かないことや痰を吐かないことなど、北京政府が躍起になってマナー向上に努めているということでした。有り難うございました。
|
|
2006年12月10日(日)晴 O. 様より
Re:「霧の桂林紀行」完成! 和田さま こんにちは。いつも素晴らしい写真をありがとうございます。「桂林特集」を楽しみにしておりました。少し前の「速報」のときに、義父に見せたらとても喜んでおりました。以前に何度か中国に出かけたことがあるものですから、懐かしいのと素晴らしい映像なのとで感激しておりました。今回の特集を見たらまた、きっと喜ぶことでしょう。思い出話に、また花が咲いて若返りの薬になります。ありがとうございました。 和田様のますますのご活躍を楽しみにしております。
|
おはようございます。早々に「霧の桂林紀行」をご覧いただき、有り難うございました。ご家族で喜んで頂ければ、作者冥利に尽きます。中国は、新旧入り交じった複雑な国で、土産物屋の売り子のしつこさなど不愉快なこともありますが、文化の違いと割り切れば気楽につきあえます。自然遺産や文化遺産を見ると、中国5000年の歴史の重みを感じます。燐国といった感じで、手軽に行けるのも良いですね。有り難うございました。
|
|
2006年12月11日(月)晴 西村文次郎 様より
Re:「霧の桂林紀行」完成! おはようございます。特集!旅紀行第22集(実質第43集)「霧の桂林紀行」完成!おめでとうございます。そしてお知らせありがとうございます。前回、速報で「霧の桂林紀行」を少し見せて頂きましたが、それを見て、完成が待ち遠しく思っていました。 800万画素2,300枚3,760MBを撮影された中から厳選し、9頁105枚にしぼりこまれたとのこと、その絞り込み作業も大変ですよね。BGMを聞きながら解説を読ませていただくのも、楽しみです。
|
おはようございます。「霧の桂林紀行」を見られて長文のお便りを頂戴し、光栄です。おっしゃるように膨大な画像から絞り込む作業は、結構大変ですが、それが楽しみでもあります。こんなものいつ撮ったのかと思ったり、それが思わぬ名作だったりして、ハプニングもあり、農家の方が収穫の喜びを感じるときと同じ気持ちになります。
|
|
2006年12月12日(火)曇 三木芳樹
様より
和田さん、こんばんは。大変ご無沙汰しております。和田さんの相変わらずの精力的な作品制作には脱帽して、興味深く拝見しております。とくに先日の「霧の桂林紀行」は感動的でした。
これまでテレビでもちょくちょく見かけますが、和田さんの詳しい解説と細部にわたる画像記録に感動致しました。谷村新司の「昴」とともに山水画の世界が流れるサントリーのCF以来、行ってみたいところの1つですがなかなか実現できません。昴の歌詞ではありませんが「あーいつの日か、誰かとこの道を」です。
|
おはようございます。お便り有り難うございました。「霧の桂林紀行」は、家内が中国に行ったことがないので、何処かに行こうと探していたところ、入門に良いということで亜熱帯の桂林を選びました。乾期なのに天気に恵まれず、気をもみましたが、結果的には水墨画の世界を堪能できました。是非、お勧めします。有り難うございました。
|
|
|
|
|
|
|
|